腹部膨満感とは
 お腹が張って苦しさや痛みを感じる状態を指します。 主な原因として、食事とともに多くの空気を飲み込むことや、腸内にガスが溜まることが挙げられます。また、便秘や特定の食品(小麦やキシリトールなどの糖類)の摂取、ストレス、運動不足も影響します。さらに、自律神経の乱れが関係する疾患、機能性ディスペプシアや過敏性腸症候群も膨満感を引き起こすことがあります。
お腹が張って苦しさや痛みを感じる状態を指します。 主な原因として、食事とともに多くの空気を飲み込むことや、腸内にガスが溜まることが挙げられます。また、便秘や特定の食品(小麦やキシリトールなどの糖類)の摂取、ストレス、運動不足も影響します。さらに、自律神経の乱れが関係する疾患、機能性ディスペプシアや過敏性腸症候群も膨満感を引き起こすことがあります。
一方で、大腸がんや腸閉塞、心不全などの病気が隠れている可能性もあります。特に激しい腹痛、呼吸困難、体のむくみ、尿量の減少が伴う場合は、早急に医療機関を受診することが重要です。
便秘が続く、げっぷやガスの回数が増える、食後や睡眠時にお腹の張りを感じる場合は、消化器内科で相談しましょう。腹部膨満感は身近な症状ですが、放置せず適切な対応を心がけることが大切です。
【原因別】腹部膨満感
(お腹の苦しい方)の症状
お腹の張り・圧迫感
- お腹が膨れているような感じがする
- 胃や腸が圧迫されるような不快感がある
- ズボンやベルトがきつく感じる
げっぷ・おならの増加
- げっぷが頻繁に出る
- おならの回数が増える
- おならが出にくく、お腹が張る
腹痛や違和感
- お腹の張りに伴う鈍痛や不快感
- 左下腹部やみぞおちの痛み
- 便秘や下痢を伴うことがある
便秘・下痢などの排便異常
- 便秘が続き、お腹が張る
- 排便後もすっきりしない
- 下痢を伴い、腸内のガスが多い
吐き気や食欲不振
- 胃の膨満感が強く、食欲がわかない
- 食後に吐き気を感じる
体のむくみ・腹水の蓄積
(重度の場合)
- お腹が異常に膨らんでいる
- 足や顔のむくみを伴う
- 肝疾患や腎疾患が原因の可能性
胸焼け・逆流性食道炎の症状
- 食後に喉のあたりがムカムカする
- 胃酸が逆流して、喉や胸が焼ける感じがする
- 仰向けで寝ると症状が悪化する
呼吸のしづらさ(重度の場合)
- お腹の膨満感が強く、呼吸が浅くなる
- 腸内ガスの過剰蓄積で横隔膜を圧迫し、息苦しさを感じる
腹部膨満感の原因・疾患
 腹部膨満感は、様々な疾患が原因で引き起こされることがあります。
腹部膨満感は、様々な疾患が原因で引き起こされることがあります。
以下に主な疾患とその症状を紹介します。
消化器系の疾患
過敏性腸症候群(IBS)
ストレスや食生活の乱れにより腸が過敏になり、腹部膨満感や腹痛を感じ、便秘や下痢を繰り返すことがあります。
機能性ディスペプシア(FD)
胃や腸に異常がないにもかかわらず、胃もたれや膨満感、食後の不快感、胃痛が生じることがあります。
便秘症
排便が滞ることで腸内にガスが溜まりやすくなり、膨満感、便の硬化、排便回数の減少、腹痛を伴うことがあります。
胃炎・胃潰瘍
胃の粘膜が炎症を起こし、胃痛、膨満感、吐き気、食欲不振、黒色便などの症状がみられます。
胃がん・大腸がん
消化器官に腫瘍ができることで消化や排便に影響を及ぼし、持続的な膨満感、食欲不振、体重減少、血便がみられることがあります。
腸閉塞(イレウス)
腸の通過が妨げられることで、激しい腹部膨満感、吐き気、腹痛、便やガスが出ないといった症状が現れます。
内分泌・代謝系の疾患
糖尿病
血糖値のコントロールがうまくいかず、消化器の働きが低下することで胃のもたれ、膨満感、体重変化、喉の渇きなどの症状が現れます。
甲状腺機能低下症
甲状腺ホルモンの不足により腸の動きが鈍くなり、便秘、膨満感、むくみ、体重増加を引き起こします。
心臓・肝臓・腎臓の疾患
心不全
心臓の機能が低下することで体内に水分が溜まりやすくなり、膨満感、息切れ、むくみ、疲れやすさがみられることがあります。
肝硬変
肝機能が低下すると腹水が溜まり、お腹の張り、食欲不振、黄疸、疲労感などの症状が現れます。
腎不全
腎臓の働きが低下すると水分や老廃物の排出がうまくいかず、膨満感、むくみ、尿量の減少、倦怠感が出ることがあります。
感染症・その他の疾患
腸内感染症(ウイルス・細菌感染)
腸内で炎症が起こることで、膨満感、腹痛、下痢、発熱がみられることがあります。
食物不耐症
(乳糖不耐症・グルテン過敏症)
特定の食品を消化できず、ガスが発生しやすくなるため、腹部膨満感、下痢、胃痛、吐き気などの症状を引き起こします。
ガスが溜まりやすい人の
対策・予防
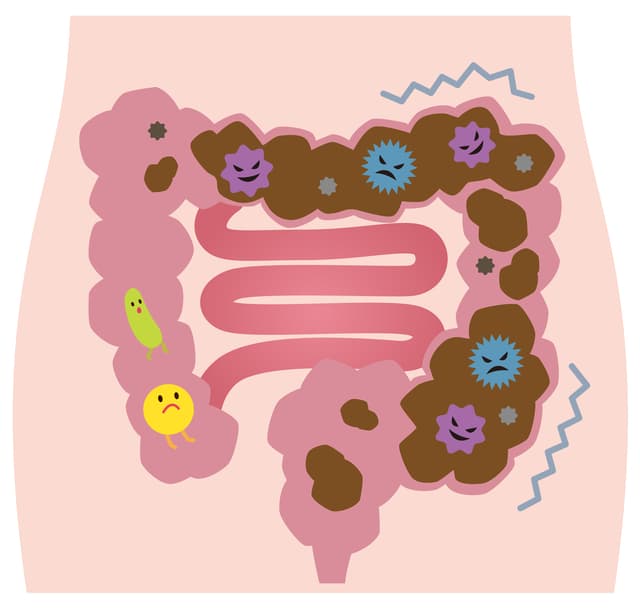
腹部膨満感を軽減・予防するためには、食生活の改善、腸内環境の整備、適度な運動、ストレス管理 が重要です。以下の方法を実践することで、症状の緩和や再発防止が期待できます。
食生活の改善
ゆっくりよく噛んで食べる
早食いや大きな口で食べると空気を一緒に飲み込みやすくなり、ガスが溜まりやすくなります。
1口30回を目安に、しっかり噛んで食べることが理想です。
過剰な食物繊維の摂取に注意する
食物繊維は腸内環境を整えるのに重要ですが、急に摂取量を増やすとガスが発生しやすくなります。
水溶性食物繊維(海藻類、納豆、オートミール) を適度に摂ることで、腸内環境を改善しながらガスの発生を抑えられます。
消化の良い食事を意識する
脂肪分の多い食事 や 揚げ物 は消化に時間がかかり、胃もたれや膨満感を引き起こしやすいため控えめにする。
温かいスープやお粥、和食中心の食事が消化に優しく、胃腸の負担を軽減できます。
ガスを発生しやすい食品を控える
豆類、キャベツ、玉ねぎ、ブロッコリー、炭酸飲料、乳製品(乳糖不耐症の場合) はガスを発生させやすいため、食べ過ぎに注意。
キシリトールやソルビトールを含む人工甘味料もガスを発生しやすい。
水分をこまめに摂取する
腸の動きを促すために 1日1.5~2リットルの水分 を摂取。
コーヒーやアルコールは腸を刺激しやすいため、摂取量を調整する。
腸内環境を整える
発酵食品を取り入れる
ヨーグルト、納豆、味噌、ぬか漬け、キムチ などの発酵食品は、腸内の善玉菌を増やし、ガスの発生を抑える。
プロバイオティクス・プレバイオティクスを活用する
プロバイオティクス(乳酸菌・ビフィズス菌を含む食品やサプリ)を摂取することで腸内環境を改善。
プレバイオティクス(善玉菌のエサとなるオリゴ糖や食物繊維)を併用すると、より効果的。
整腸剤を活用する
市販の整腸剤(ビオフェルミン、ラックビーなど)は腸内のバランスを整え、膨満感の軽減に役立つ。
症状が続く場合は、医師に相談して適切な薬を処方してもらう。
適度な運動をする
軽い有酸素運動を取り入れる
ウォーキング、ヨガ、ストレッチ などの軽い運動を毎日20~30分行うと、腸の動きを促進し、ガスの排出を助ける。
ヨガの「ねじりのポーズ」 や 「キャット&カウポーズ」 は腸を刺激し、ガスの排出を促進。
腹式呼吸を行う
深くゆっくりした呼吸をすることで、腸の動きが活発になり、膨満感の軽減に繋がる。
1回3~5分、1日2~3回 を目安に行うと効果的。
ストレス管理をする
自律神経を整える
ストレスが腸の動きを低下させる原因となるため、リラックスできる時間を作る。
深呼吸、瞑想、軽いストレッチ を日常的に行うと、腸の調子を整えやすくなる。
睡眠をしっかり取る
1日7~8時間の睡眠 を確保し、腸のリズムを整える。
夜遅い食事は消化不良を引き起こしやすいので、就寝2~3時間前までに食事を済ませる。
便秘や下痢を防ぐ
排便リズムを整える
毎朝決まった時間にトイレへ行く習慣をつけ、腸を刺激する。
食物繊維+水分+運動 を組み合わせることで、腸の蠕動運動を促す。
下痢を防ぐための食事管理
辛いもの、脂っこいもの、冷たい飲み物 は腸を刺激しすぎるため、摂取を控える。
過敏性腸症候群(IBS)の人は、低FODMAP食(発酵しやすい糖質を減らす食事法) を試してみるのも有効。
生活習慣の見直し
姿勢を改善する
猫背や長時間の座り姿勢は腸を圧迫し、ガスが溜まりやすくなるため、背筋を伸ばして座る習慣をつける。
入浴で血流を促す
38~40℃のぬるめのお湯に浸かることでリラックスし、腸の動きが活発になる。
腹部膨満感による検査の
重要性
腹部膨満感は、ガスの蓄積や消化不良などの一時的なもの から、腸閉塞や大腸がん、肝疾患などの重大な病気の兆候 まで幅広い原因が考えられます。
そのため、原因を特定し、適切な治療を行うためには早期の検査が重要 です。
腹部膨満感に対する
大腸カメラ検査

大腸カメラ検査では、便秘や腸閉塞、大腸ポリープ、大腸がん、炎症性腸疾患などの大腸の異常を評価し、過敏性腸症候群(IBS)や小腸内細菌異常増殖症(SIBO)など、腸内ガスの過剰な蓄積を引き起こす疾患を診断するのに役立ちます。
よくある質問(Q&A)
お腹がパンパンに張る原因は何ですか?
主な原因は腸内にたまる空気やガスです。早食い、炭酸飲料の摂取、ガムや飴による唾液と一緒の空気の飲み込み、ストローでの飲み物摂取、会話をしながらの食事などが典型です。さらに、便秘や腸の動きの低下によりガスが滞留しやすくなったり、乳糖や小麦など特定食材に対する不耐症でも張りを感じやすくなります。加えてストレスによる自律神経の乱れは腸の働きを弱め、膨満感を悪化させる一因です。腹部手術後の癒着や内服薬(鉄剤、便秘薬の乱用、糖尿病治療薬など)も要因となるため、背景に複数の因子が重なっているケースも多いのが特徴です。
そんなに食べてないのにお腹が張るのはなぜ?
摂取量よりも“食べ方”や“食材の質”に問題がある場合が多いです。例えば人工甘味料(キシリトールやソルビトール)、玉ねぎやキャベツ、豆類などは少量でも腸内で発酵してガスを発生させやすい食品です。また、早食いや飲み込み癖、食後すぐに横になる姿勢も空気の取り込みやガス排出の妨げになります。さらに小腸内細菌異常増殖症(SIBO)があると、少しの食事でも腸内発酵が過剰に起こり、強い張りにつながります。食事の量に比例しない膨満感が続く場合は、こうした機能的な要因を疑う必要があります。
お腹が張る感じはガンの症状ですか?
膨満感の多くは一時的で良性の要因によるものですが、中には消化器がんや婦人科腫瘍など重い疾患のサインであることもあります。特に「体重減少」「血便や便が細くなる」「原因不明の貧血」「夜間の腹痛」「発熱」を伴う場合は要注意です。大腸がんや卵巣腫瘍、腹水を伴う疾患などが考えられます。症状が数週間以上続き改善しない、あるいは家族に大腸がんの既往がある方は、消化器内科での精密検査や婦人科でのチェックを早めに受けることが大切です。
お腹のガス抜きを即効でするには?
即効性のある方法としては、①うつ伏せで深呼吸を繰り返す、②膝を抱える“ガス抜きのポーズ”、③左右にゆっくり体を転がす、④おへそを中心に“の”の字を描くように腹部をマッサージ、などがあります。これらは腸の動きを刺激してガスの排出を促します。また、硬い衣類やベルトを緩める、温かい白湯を少しずつ飲むのも有効です。食後は背筋を伸ばし、前屈みを避け、10〜15分の軽い散歩を行うことで腸の動きが改善され、ガス抜きがスムーズになります。
お腹の張りが危険なサインは?
注意すべきサインには次のようなものがあります。①強い持続的な腹痛、②嘔吐を伴う、③便やガスがまったく出ない、④発熱、⑤血便や黒色便、⑥腹部の急な膨隆や左右差、しこりを触れる、⑦呼吸困難や下肢のむくみ。これらは腸閉塞、腸出血、心不全、腹水の可能性があり、放置すると命に関わります。市販薬や鎮痛剤でごまかすと診断が遅れるため、これらの症状があれば直ちに医療機関を受診してください。
お腹が張る感じ(腹部膨満感)は何科を受診すべき?
基本は消化器内科を受診するのが適切です。問診を行い、必要があれば大腸内視鏡を実施します。下腹部の張りに月経異常や婦人科症状を伴う場合は婦人科も併診が望ましいです。複数の診療科が関わるケースもあるため、最初は総合的に判断できる内科を受診するのが安心です。
快便なのにお腹が張る病気は?
排便が毎日あっても腹部膨満感が続く場合、機能性ディスペプシア(胃の働きが弱い)、過敏性腸症候群(便通はあるがガスが過剰)、小腸内細菌異常増殖症(SIBO)、胆のうや膵臓の機能低下、乳糖不耐症や小麦に含まれるフルクタンへの過敏症などが考えられます。便の状態が良くても「食後すぐに張る」「げっぷやガスが多い」といった特徴がある場合は、機能性疾患の可能性を考慮して医師に相談すると安心です。




